不倫とひとえに言ってしまえば、世の中的には少々「悪者扱い」だが、映画はそれを美しく美化することができる。
デヴィット・リーン監督が描いた純真な不倫の物語『逢びき』と同じく、亭主を持ちながらも別の人を愛してしまう女性を描いたのが『キャロル』だ。
本記事では、ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラが主演を務めた映画『キャロル』について語っていく。
映画『キャロル』あらすじと概要

1952年のクリマスシーズンに、デパートのおもちゃ売り場でアルバイトをしていたテレーズは、お客さんとして現れた美しい婦人に魅入られる。その婦人が忘れていった手袋を送ったお礼にと、食事へ招待されたテレーズ。婦人の名はキャロルといい、テレーズは次第に惹かれていくのだが…。
【監督】
トッド・ヘインズ
【出演】
ケイト・ブランシェット(キャロル)
ルーニー・マーラ(テレーズ)
【日本劇場公開日】
2016年2月11日
【時間】
118分
【国】
アメリカ
映画『キャロル』の考察レビュー※ネタバレ注意
ここからは本編の内容と結末に触れています。まだ観賞していない方はご注意ください。
1950年代をノストラジックな映像と共に、エレガントに仕上げた『キャロル』。デパートの売り場で偶然出会った女性同士の恋模様を、現実的な問題を絡めながら複雑かつ純粋に描いた珠玉のラブストーリーだ。
ここからは映画『キャロル』の本編に関わる考察を行うため、まだ観賞していない方は注意してほしい。
高校生の頃にはわからなかった親権と自分の在り方を問う複雑さ

筆者は高校生の頃に『キャロル』を観た。だが、高校生の頃の筆者では到底わかり得ない複雑さがあった。
その複雑さの原因こそ、子どもの存在である。
本作はキャロル側に旦那と子どもがいる。この二人はすでに冷え切った関係のもと暮らしており、キャロルが離婚を切り出していた。離婚には、当然考えるべき子どもの存在があり、実際に作中で二人は親権について揉めている。
高校生の僕は、この事実こそ捉えられたものの、単に映画の主人公であるキャロルの味方をしていた。これは単純かつ軽率な見方だと気がついたのは、僕が子どもを持ち、一年が過ぎた頃に再度『キャロル』を観たときである。
本作で描かれている夫婦の問題には、キャロル側にも旦那側にも事情があり、それぞれの環境や相手への想い、互いの感情などが複雑に絡み合っている。僕が妻と喧嘩する時も、必ず子どもの話が出てくるし、お互いが意固地になって譲らない結果、酷いことを言ってしまうこともある。そうして譲れなくなった先に、キャロル夫婦のような結末が待っているのかもしれないと思った。
だからこそ、二人のどちらかが悪いという見方は、安易にできないと感じたのだ。

結局はキャロルが親権を譲り、涙ながらに「自分らしさを押し殺すことに耐えきれない」と語ってテレーズに会いに行く。
人間には男と女の二つの性があり、同じ性が交わることのないこの世界において、同性愛は異常とも捉えられてしまう。これは本作の中でも“キャロルに親権が渡らない理由”として持ち込まれており、曖昧でありながらもはっきりと同性愛者の偏見が突きつけられているのだ。
単純に感情の話だけでは片付けられない親権問題。キャロルの感情は、物語の主人公だからこそ観客の共感を誘いやすいが、その背景にあるさまざまな問題は我々には決して見えない。その背景を想像するだけで、旦那の気持ちも察することは可能になると思った。

そして、キャロルが子どもの親権を譲ってでも自分を壊してはいけないと考えたことにも、英断だと拍手を送りたいと思った。仮に何らかの理由で離婚となっても、やはり僕も子どもは絶対に渡したくない。でも、アイデンティを壊してしまうのは、一人の人間として苦痛を通り越して地獄である。
キャロルは母親としての自分と、本来の自分との間で悩みに悩んで苦しんだ。その結果を見届けることは、我々観客にとっても“自分の在り方を問う”貴重な機会となるだろう。
キャロルの旦那は悪なのか?

キャロルは同性愛者だ。しかし、旦那はまだキャロルを愛していた。親権の問題は然り、テレーズとの旅の途中で脅しのような手紙をよこし、キャロルを強制的に引き戻したのは悪だったのか?
答えは、YES。
であったが、今はNOだ。一見旦那が悪に見えるようだが、筆者にとってはどうも片側だけが悪いとは思えない。
旦那はキャロルのことを愛していたし、子どもができるまでに至ったのだから、やはりキャロルが自分を好きではないと知るのは悔しいし悲しい。感情的になるほど嫌で仕方がないし、それは憎しみや嫉妬となって意固地になることもあると思う。僕もおそらく好きな妻に嫌われたら、すごく悔しいし憤りを感じてしまうから。
それでも旦那は、キャロルともう一度やり直せるかと努力したのだ。もちろん一方的ではあるかもしれないが、キャロルの理由も理由で自分勝手な側面もある。
だから旦那を責める気にもなれない。

もちろんキャロルは自分の心に従うべきだし、世の中に合わせて本来の自分を押し殺す必要もない。同性愛が一般的になりつつある現代とは違い、1950年代だから、より一層自分らしさを突き通すのが難しいのもわかる。だからこそ複雑で難しい問題なのだと気がついたのだ。
キャロルも旦那も、悪くない。やがて双方にベスト道が見つかったのなら、私は良いのではないかと思う。
デビット・リーン監督の『逢びき』を彷彿とさせる構成とラスト

キャロルは旦那との親権問題に決着をつけ、ラストでは自分らしくありたいと願いテレーズを再び誘いにカフェで待ち合わせをする。久しぶりの再会を果たしたキャロルとテレーズの場面は、冒頭のシーンへとつながる。
構成としては冒頭から回想に入り、テレーズとキャロルの出会いから今(冒頭)に至るまでを描いている。〈冒頭→回想→出会い→冒頭→ラスト〉
本作のラストは、テレーズがキャロルの誘いを断るも、結局キャロルのもとへと足を運び、キャロルと目を合わせて終了するというもの。
つまり、テレーズはキャロルと再び結ばれることを選んだのだ。
〈冒頭→回想→出会い→冒頭→ラスト〉の構成は、そう、筆者の僕も敬愛するデビット・リーン監督の『逢びき』の構成と、まったく同じもの。実際、キャロル役のケイト・ブランシェットはインタビュー時に「逢びきのオマージュ」だと語っている。
巧みな構成術をオマージュしながらも独自のラストへと展開していく『キャロル』は、やはり秀逸であるとわかる。



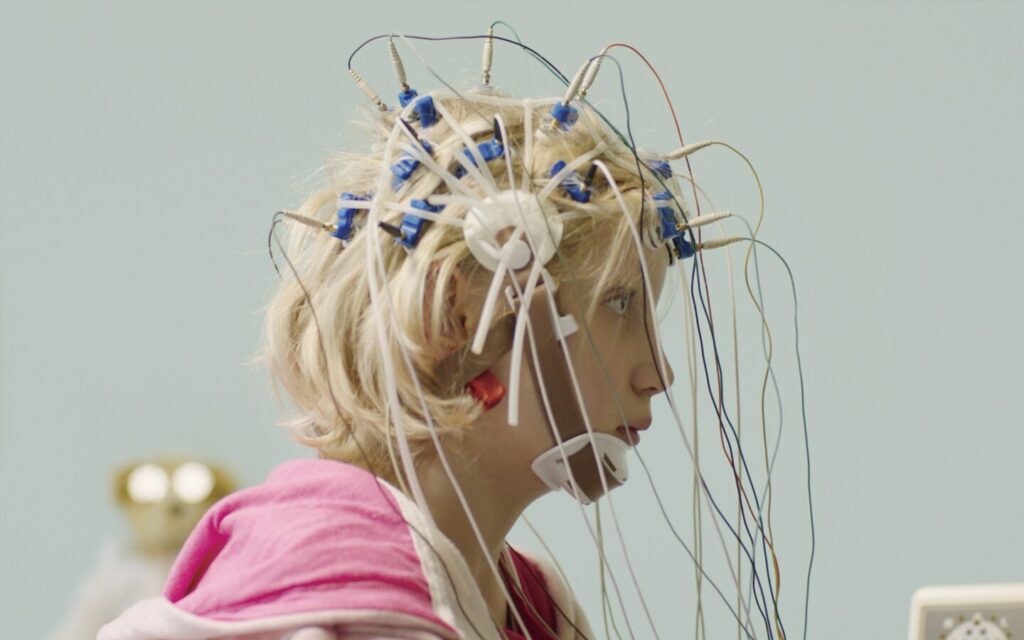












コメント